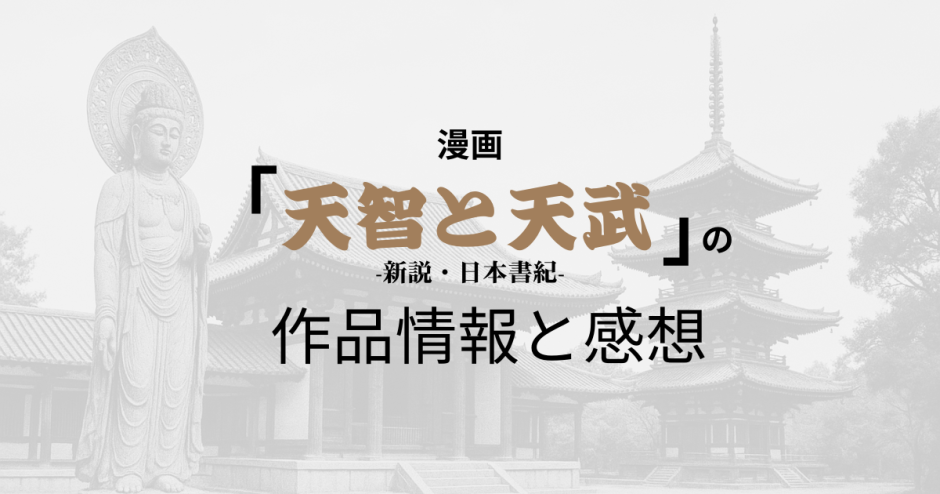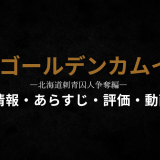中村真理子による歴史漫画「天智と天武―新説・日本書紀―」は、古代日本の謎に満ちた時代を舞台に、兄弟の対立と壮絶な人間ドラマを描いた作品です。
原案監修は園村昌弘氏が務め、小学館の「ビッグコミック」にて2012年から2016年まで連載されました。
単行本は全11巻が刊行されています。
物語の主軸となるのは、中大兄皇子(のちの天智天皇)と大海人皇子(のちの天武天皇)という、日本史でも有名な兄弟です。
二人の関係を「新たな説」に基づいて描くことで、従来の歴史観に一石を投じる意欲作となっています。
物語は、明治時代にさかのぼります。
岡倉天心とアーネスト・フェノロサが法隆寺・夢殿の秘仏「救世観音」に対面する場面からはじまります。
1200年もの間封印されていたその仏像の後頭部には、釘が打ち込まれていました。
なぜ聖徳太子の姿を写したとされる仏像が、これほどまでに恐れられたのか?
この謎が物語の出発点となり、「大化の改新」にまつわる真相、そして天智と天武をめぐる数奇な運命へと繋がっていきます。
本作では、通説で語られる「大化の改新」――中大兄皇子と中臣鎌足が悪政を行っていた蘇我入鹿を討ったという英雄譚――を、まったく異なる角度から捉えています。
実は中大兄皇子と中臣鎌足こそが野心に満ちた側であり、彼らによるクーデターだったという大胆な解釈がなされます。
さらに、中臣鎌足は百済の王子・豊璋だったという設定も登場します。
そして、大海人皇子は蘇我入鹿と皇極天皇(のちの斉明天皇)との間に生まれた子であるという設定も加わり、物語はいっそう複雑で深いものになります。
その結果、天智と天武の関係は単なる異父兄弟ではなく、「父の仇」と「その子」という、愛憎入り混じる因縁に満ちたものとして描かれます。
歴史の裏側にあるかもしれない「もしも」に果敢に切り込みながら、スリリングな展開と重厚な人間模様を描いた本作は、歴史漫画の枠を超え、多くの読者の心を掴みました。
この記事では、天智と天武―新説・日本書紀―」のあらすじや登場人物の魅力、読者の感想、作品の評価、さらには作者についてもご紹介します。
本の情報

| 出版年月 | 2013年2月28日(1巻発売) – 2016年8月30日(11巻発売) |
| 著者 | 作画:中村真理子、原案監修:園村昌弘 |
| 出版社名 | 小学館 |
| 発行形態 | 漫画単行本(コミックス) |
| レーベル | ビッグコミックス |
| 巻数 | 全11巻 |
| 価格 | 607円(税込) |
「天智と天武-新説・日本書紀-」のあらすじ

この物語は、古代日本の歴史を大きく動かした二人の皇子、中大兄皇子(のちの天智天皇)と大海人皇子(のちの天武天皇)を中心に展開します。
通説では異父兄弟とされる二人ですが、本作ではさらに衝撃的な「新説」が描かれています。
なんと、大海人皇子は、蘇我入鹿と皇極天皇(のちの斉明天皇)との間に生まれた“不義の子”であるという設定です。
物語が動き出すのは、645年の「乙巳の変」。
中大兄皇子は、母の愛人であり、自らも特別な想いを抱いていたとされる蘇我入鹿を、母・皇極天皇の目の前で暗殺します。
この行動により、中大兄皇子は、大海人皇子にとって「異父兄」でありながら「父の仇」となるのです。
父を殺された大海人皇子は、復讐の想いを胸に秘めながら、兄・中大兄皇子に近づいていきます。
しかし、二人の間にあるのは、ただの憎しみではありません。
入鹿に生き写しの大海人皇子に対し、中大兄皇子は強く惹かれていきます。
一方で、大海人皇子も兄に対して複雑な感情を抱くようになり、やがて二人の関係は愛憎の渦に呑みこまれていきます。
物語は、そんな二人の皇子の心の揺れ動きとともに、政治の闇、権力の陰謀、そして禁断の感情が絡み合う展開へと進んでいきます。
さらに注目すべきは、中大兄皇子の側近として登場する中臣鎌足の存在です。
彼は、百済からの亡命王子・豊璋であり、母国再興という野望を胸に中大兄皇子を操ろうとします。
この作品は、日本最古の歴史書「日本書紀」に記された記録を、まったく別の視点から読み解こうとする挑戦でもあります。
歴史は勝者によって書かれる。
その考え方を軸に、「入鹿は本当に悪人だったのか?」「聖徳太子とは何者だったのか?」など、教科書には描かれない“もしも”の物語が浮かび上がります。
また、物語には法隆寺の秘仏「救世観音」にまつわる謎も登場します。
その仏像の後頭部に打ち込まれた釘の意味とは何なのか。
そこに込められた想いが、古代史最大のミステリーへと繋がっていきます。
定説を覆す大胆な発想と、登場人物たちの激しい感情が交錯する「天智と天武」は、まさに歴史ロマンの醍醐味を味わえる一冊です。
「天智と天武-新説・日本書紀-」の登場人物紹介

中大兄皇子(なかのおおえのおうじ/のちの天智天皇)
皇極天皇(斉明天皇)の息子。
母の愛人であり、自らも密かに想いを寄せていたとされる蘇我入鹿を、自らの手で暗殺するという重い決断を下した人物です。
権力への執念を持ち、冷静かつ計算高い策略家として描かれる一方で、異父弟である大海人皇子に対しては、複雑な感情を抱いています。
その心の中には、憎しみと愛情、そして孤独や葛藤が交錯していて、単なる「悪役」には収まらない深みがあります。
作中では「ハイパーエリートで情緒不安定なイケメン策士」とも評される、強烈な個性を放つ人物です。
大海人皇子(おおあまのおうじ/のちの天武天皇)
物語の中核を担う存在であり、作品最大の「新説」が彼に関わっています。
本作では、蘇我入鹿と皇極天皇の間に生まれた子という設定となっていて、中大兄皇子にとっては「異父弟」であると同時に「父の仇」となる人物です。
復讐心を抱きながら中大兄皇子に近づきますが、やがて兄に対して複雑な感情を抱くようになります。
外見は爽やかな青年でありながら、内には鋭い知性と深い憎しみを秘めていて、静かなる策士として描かれます。
また、幼少期は存在を隠され、入鹿が作った“隠れ里”で育てられたという設定が、彼の神秘性をいっそう際立たせています。
蘇我入鹿(そがのいるか)
蘇我氏の頂点に立つ権力者。
歴史上では専横を極めた悪人とされていますが、本作では先進的で開明的な思想を持つカリスマとして描かれています。
唐との外交を試みるなど、時代を先取りするような人物像が浮かび上がります。
皇極天皇との関係も描かれ、大海人皇子の父であるという設定が物語に深く関わってきます。
中大兄皇子により暗殺されることで、大化の改新と兄弟の運命が大きく動き出します。
さらに、哲学者・梅原猛氏の説を元に、聖徳太子の正体が入鹿であった可能性まで示唆される、極めて重要な存在です。
豊璋(ほうしょう)/中臣鎌足(なかとみのかまたり)
本作では、中臣鎌足の正体が百済から亡命した王子・豊璋であるという大胆な解釈が取られています。
亡国となった百済の再興を胸に秘め、中大兄皇子に取り入り、政治の実権を握ろうとする策士として登場します。
冷徹な戦略家として描かれる一方で、息子・定恵への複雑な想いも描かれ、人間的な深みも与えられています。
物語全体のキーパーソンとして、裏から歴史を動かす存在です。
その他の登場人物
- 藤原不比等(ふじわらのふひと)
後に権力を握り、「日本書紀」の編纂を主導したとされます。天武天皇と蘇我氏の影を歴史から消そうとしたとされる人物です。 - 金春秋(きんしゅんしゅう)
新羅の王。大海人皇子とは旧知の仲であり、親しい関係を築いています。 - 行信(ぎょうしん)
高僧であり、大友皇子の孫とされています。蘇我入鹿の霊を鎮めるため「聖徳太子」として祀り上げた人物とされ、法隆寺夢殿の秘仏・救世観音にまつわる謎とも関わりを持ちます。 - カササギ
大海人皇子に仕える従者。入鹿が築いた“隠れ里”の出身で、忍びのような技を持つ一族の一員として活躍します。
「天智と天武-新説・日本書紀-」をネットで調べた他の読者の声

「天智と天武―新説・日本書紀―」は、その大胆な設定と重厚な人間ドラマによって、多くの読者の関心を集めている作品です。
インターネット上の感想やレビューをのぞいてみると、その評価はおおむね好意的でありながら、いくつかの注目すべき賛否も見られます。
まず多くの読者が挙げているのは、物語の設定と展開の面白さです。
通説とは異なる「新説」。
たとえば大海人皇子が蘇我入鹿の子であることや、中臣鎌足が百済からの亡命王子・豊璋であるという仮説などが、歴史の裏側に切り込む物語として高く評価されています。
まるで壮大な歴史ミステリーを読み解くような感覚で、物語に没入できたという声も多く、歴史の常識を疑いながら読むスリルが魅力のひとつとされています。
登場人物たちの描き方もまた、多くの読者の心をつかんでいます。
中大兄皇子は、冷徹で知略に長けたエリートでありながら、複雑な感情を内に秘めた人物として描かれています。
一方の大海人皇子は、一見穏やかな風貌の裏に鋭い知性と復讐心を隠し持つ策士です。
この二人の関係性には単なる善悪を超えた奥行きがあり、キャラクター同士の感情の揺らぎに惹き込まれたという読者も多く見受けられます。
作画についても高く評価されています。
中村真理子による描線は繊細かつ力強く、とくに人物の表情や劇的な場面の構図が印象的で、物語の緊迫感を高めています。
劇画風の絵柄が本作の持つ重厚な世界観とよく合っていて、絵の力でも作品の魅力が際立っていると感じる読者が多いようです。
また、日本古代史に詳しくない人でも楽しめる点も好意的に受け止められています。
作品全体がひとつのフィクションとして丁寧に構築されているため、歴史の知識がなくても人間ドラマや物語の流れをしっかりと追うことができます。
むしろ、この作品を通じて古代史に興味を持ったという声も少なくありません。
一方で、本作には賛否が分かれる要素もあります。
中でも多く取り上げられているのが、登場人物同士の関係に見られる「ボーイズラブ的な描写」についてです。
天智と天武の間に描かれる強い執着や深い絆は、読む人によってはBL的な要素として受け取られることもあるようです。
表紙の雰囲気からそう感じたという人もいて、とくに九巻の展開に驚きを覚えた読者もいたようです。
ただし、あくまで心理描写の一環であり、直接的な場面は描かれていないとする意見も多く、読み方によって印象は変わる部分でもあります。
また、作品全体に漂う雰囲気が、山岸凉子の「日出処の天子」と似ていると感じる読者もいました。
とくに古代の皇子たちの複雑な心の葛藤や、濃密な関係性を描く点において、比較対象として名前が挙がることが多いようです。
さらに、一部の読者からは、設定が大胆すぎることに違和感を覚えたという声も聞かれました。
とりわけ、蘇我入鹿の描かれ方については、実在の人物像からかけ離れて聖人のように持ち上げられているのではないか、という意見もあり、史実との距離感に戸惑いを覚える人もいるようです。
とはいえ、全体としては、歴史の「もしも」を大胆に描いたこの作品は、多くの読者にとって刺激的で読み応えのある一冊として受け入れられています。
定説にとらわれず、自分なりの視点で歴史を楽しみたいという人には、とくにオススメできる作品です。
「天智と天武-新説・日本書紀-」の評価と感想

「天智と天武―新説・日本書紀―」は、古代日本の歴史に大胆な仮説を交えて描かれた意欲作です。
とくに天智天皇と天武天皇をめぐる複雑な人間関係と歴史的事件を、まったく新たな視点から描いていて、その構想力と表現力の高さが高く評価されています。
この作品の最大の魅力は、既存の歴史観に真っ向から挑んでいる点にあります。
たとえば、大海人皇子を蘇我入鹿の子として描いたり、中臣鎌足の正体を百済からの亡命王子・豊璋とするなど、常識を覆すような設定が数多く登場します。
そうした大胆な解釈は、古代史に興味を持つ読者の知的好奇心を刺激し、歴史は勝者によって書かれるという視点から、別の物語を見出そうとする試みに繋がっています。
とくに、法隆寺に安置されている救世観音の謎を物語の導入とする構成は秀逸で、読者を一気に古代の闇へと惹き込む力があります。
登場人物たちの人間関係や心理描写も見どころのひとつです。
天智と天武は、兄弟でありながら父の仇でもあり、互いに強く惹かれ合うという複雑な関係にあります。
その愛憎入り混じる感情や、権力をめぐる策略、深い孤独と執着が丁寧に描かれていて、歴史作品という枠を超えた重厚な人間ドラマを堪能することができます。
とりわけ、対立しながらも互いを意識し続ける二人の心理の揺れ動きは、物語全体の緊張感と厚みを生み出しています。
作画もまた高く評価されている要素です。
中村真理子が描く劇画的な筆致は、登場人物の感情や場面の迫力をより引き立てています。
戦いや儀式の場面では古代日本の雰囲気が色濃く漂い、人物の表情には細やかな感情の動きが込められていて、読む者に強く印象を残します。
一方で、注意すべき点もいくつかあります。
まず、史実との距離感についてです。
本作は「新説」として創作された物語であり、教科書的な正確さを重視する読者にとっては、設定に違和感を覚えるかもしれません。
史実と異なる点が多いからこそ、あくまでフィクションとして楽しむ姿勢が必要となります。
また、天智と天武の関係には、兄弟愛や友情を超えた強い執着が描かれていて、読者によってはそれがボーイズラブ的な要素として感じられる場合もあります。
直接的な表現こそ少ないものの、感情の交錯や関係性の濃さは際立っていて、この点に抵抗がある読者にとっては好みが分かれるかもしれません。
ただし、それを深い感情表現の一環として捉えれば、作品の主題である愛と憎しみの交錯をより深く味わうことができます。
さらに、大海人皇子の出生や中臣鎌足の正体に関する設定があまりにも大胆であるため、「とんでも説」として受け止める向きもあります。
しかし、これらの設定には、梅原猛氏をはじめとする学者の論考を下敷きとした背景があり、決して突飛な空想ではなく、一定の考察に基づいた構成となっています。
総じて、「天智と天武―新説・日本書紀―」は、歴史の定説にとらわれず、想像力と創造力で新たな物語を描き出した力作です。
古代史の「もしも」に興味がある方や、濃密な人間関係に惹き込まれたい読者にとっては、読み応えのある一冊となることでしょう。
史実とは異なる解釈や関係性に対して柔軟な姿勢で臨めば、きっとこの作品が持つ奥深さと面白さに心を動かされるはずです。
「天智と天武―新説・日本書紀―」をチェックする
「天智と天武-新説・日本書紀-」のオススメの読者層

「天智と天武―新説・日本書紀―」は、古代史をテーマにした作品でありながら、単なる歴史漫画にとどまらず、濃密な人間ドラマと大胆な仮説で読者を惹きつけます。
そのため、読者の興味関心によって、さまざまな角度から楽しめる一冊となっています。
とくに、以下のような読者にとっては、深く心に残る作品となることでしょう。
- 日本の古代史に興味がある方
飛鳥時代の政治背景や大化の改新、壬申の乱といった出来事を題材にしていて、教科書で触れた歴史を別の視点から捉え直す機会を与えてくれます。
天智天皇や天武天皇、蘇我入鹿、中臣鎌足といった実在の人物たちが、ドラマティックに再構築されて描かれているため、歴史の表と裏を同時に味わいたい方にぴったりです。 - 歴史ミステリーや「もしも」の物語が好きな方
法隆寺の救世観音に秘められた謎や、聖徳太子の正体に関する大胆な仮説など、「歴史の裏側に隠された真実」を探るミステリー的な要素が満載です。
歴史を題材としながらも、自由な発想で物語が展開されるため、「もし歴史がこうだったら」と想像するのが好きな方にとっては、非常に魅力的な内容になっています。 - 愛憎が入り混じる重厚な人間ドラマを楽しみたい方
主人公である天智と天武の関係性は、兄弟という枠にとどまらず、父の仇や深い執着を抱える相手として、複雑な感情を描き出しています。
表面的な対立だけでなく、内に秘めた孤独や野望、禁断の想いなどが丁寧に描写されていて、人間の本質に迫る物語として、深い読後感を残してくれます。 - 表現力豊かな劇画調の作画が好きな方
中村真理子による作画は、人物の感情や場面の緊張感を巧みに描き出していて、視覚的にも物語の魅力を強く支えています。
華やかで迫力のある筆致は、作品全体に重厚な空気を与えていて、歴史ロマンの世界観をより深く楽しみたい方にオススメです。 - BL的な関係性に興味がある、または抵抗がない方
天智と天武の間には、兄弟愛を超えた強い絆や執着が描かれていて、いわゆるBL的な雰囲気を感じ取る読者もいます。
明確に描かれているわけではありませんが、関係性の濃さや心理描写の細やかさから、そうした要素を楽しめる方であれば、より深く物語に入り込めることでしょう。
もし、こうした要素にひとつでも心惹かれるものがあれば、ぜひ一度「天智と天武―新説・日本書紀―」を手に取ってみてください。
壮大な歴史と人間の情念が交錯する世界が、あなたの中に新たな古代史のイメージを描き出してくれるはずです。
「天智と天武-新説・日本書紀-」を読んだ方にオススメの類似作品の紹介

「天智と天武―新説・日本書紀―」は、古代日本を舞台にした壮大な歴史ドラマと、人間関係の複雑な機微を描いた作品です。
その魅力に惹き込まれた方には、次のような作品もオススメです。
どれも時代背景やテーマ、作風に共通点があり、さらに深い歴史の世界を味わうことができます。
- 「卑弥呼」(作画:中村真理子、原作:リチャード・ウー)
「天智と天武」の作画を手がけた中村真理子が、別の作品でも古代日本を舞台に描いています。
弥生時代の女王・卑弥呼を中心に、神話と政治が交錯する時代を重厚に描いた物語です。
美麗で迫力ある画風が、神秘的な古代の雰囲気と見事に調和していて、中村真理子の作画に惹かれた方にはとくにオススメです。 - 「日出処の天子」(作:山岸凉子)
聖徳太子をモデルにした主人公が、予知能力を持つ美しい少年として描かれる少女漫画の金字塔です。
同性愛的な描写や政治的陰謀、人間の葛藤を織り交ぜた独自の解釈が、多くの読者の心をつかみました。
古代の皇子たちの内面に深く迫る点で、「天智と天武」との共通点が多く、BL的な要素に興味のある方にも響く作品です。 - 「天上の虹」(作:里中満智子)
持統天皇を主人公に据えた長編歴史漫画で、天智・天武の時代を別の視点から詳細に描いています。
政治の舞台裏や、王族の人間模様、女性としての生き様が丁寧に描かれていて、重厚な物語をじっくり読みたい方に適しています。
同じ時代を異なる視点で見ることで、「天智と天武」との対比も楽しめるでしょう。
これらの作品は、いずれも歴史の裏に潜む人間のドラマや、時代を超えたテーマに深く切り込んでいます。
「天智と天武」の読後に、さらに歴史の奥深さや想像の広がりを味わいたいと感じた方は、ぜひこれらの作品にも触れてみてください。
きっと、新たな発見と感動が待っていることでしょう。
著者について

「天智と天武―新説・日本書紀―」は、その大胆な構成と緻密な描写により、多くの読者を惹きつけています。
その完成度の高い作品世界を支えているのが、作画を担当した中村真理子氏と、原案監修を務めた園村昌弘氏です。
それぞれの経歴や作品背景を知ることで、本作の深みをよりいっそう味わうことができます。
中村真理子(なかむら まりこ)
本作の作画を手がけた中村真理子氏は、1959年3月29日、和歌山県和歌山市に生まれました。
武蔵野美術大学を卒業後、小池一夫氏が主宰する「劇画村塾」で学び、1980年に「運命のファースト・キッス」で漫画家としてデビューを果たします。
デビュー当初は、小池一夫氏や狩撫麻礼氏といった実力派の原作者と多くの作品を共作し、「ギャルボーイ!」「天使派リョウ」などの人気作品を生み出しました。
その後も一貫して、人物の感情を丁寧に描くドラマ性のある作風と、確かな画力で評価を集めてきました。
感情表現の豊かさや、登場人物たちの生き生きとした描写は、中村氏の大きな魅力のひとつです。
園村昌弘氏とのコンビでは、本作のほかに、映画監督・黒澤明の人生を描いた伝記作品「クロサワ/炎の映画監督・黒澤明伝」も手がけていて、同作は2001年に文化庁メディア芸術祭マンガ部門で優秀賞を受賞するなど、高い評価を受けています。
2025年現在は、同じく小学館の「ビッグコミック」にて、リチャード・ウー氏を原作に迎えた「卑弥呼」を連載中です。
こちらも日本古代史を舞台にした壮大な物語であり、「天智と天武」で中村氏の絵に魅せられた読者にとっては必読の作品と言えるでしょう。
長年にわたり青年誌を中心に活躍してきた、実力派の漫画家です。
園村昌弘(そのむら まさひろ)
本作で原案監修を務めた園村昌弘氏は、プロフィールが多く公開されている人物ではありませんが、先述の「クロサワ」でも中村真理子氏とコンビを組んでいて、緻密な歴史考証と独自の視点を活かした構成力に定評があります。
「天智と天武」では、梅原猛氏の学説などを土台としながらも、あくまで独自の歴史観をもとに物語を構築。
歴史的事実と大胆な仮説を組み合わせ、ドラマとしての面白さを最大限に引き出す役割を果たしました。
登場人物の設定や関係性、物語の進行において、骨太な構成を支えた重要な存在と言えるでしょう。
この二人の力が結集することで、ただの歴史漫画では終わらない、濃密な人間ドラマと知的な興奮をもたらす作品が誕生しました。
「天智と天武―新説・日本書紀―」は、まさに中村氏の確かな筆致と園村氏の構想力が見事に融合した、現代の歴史漫画の中でも際立った一冊です。
「天智と天武-新説・日本書紀-」のよくある質問

- 歴史に詳しくなくても楽しめますか?
- はい、大丈夫です。
本作は古代日本を舞台にしていますが、中心にあるのは天智と天武という二人の皇子の複雑な人間関係です。
愛憎入り混じる感情の交錯や権力闘争のドラマが主軸となっていて、歴史に詳しくなくても十分に惹き込まれる内容になっています。
むしろ、この物語をきっかけに古代史に興味を持つ方も少なくありません。
もちろん、ある程度の歴史的知識があれば、通説との違いや「新説」とされる部分をより深く味わうことができます。
- 「日本書紀」とどれほど違う内容ですか?
- かなり異なります。
「日本書紀」では、天智天皇を正統な王として描く傾向が強いとされていますが、本作ではその記述に対して真っ向から新しい視点を提示しています。
たとえば、大海人皇子(後の天武天皇)を蘇我入鹿の子とし、中臣鎌足を百済の王子・豊璋とするなど、通説とはまったく異なる仮説が物語の中核をなしています。
この作品は、あくまで「勝者が書いた歴史」の裏にあるかもしれない別の可能性を描くフィクションとして楽しむのが良いでしょう。
- 物語の終わり方は史実に沿っていますか?
- 大筋では史実に沿っています。
たとえば壬申の乱の結末など、実際の歴史の流れに準じた展開が描かれています。
ただし、登場人物の動機や行動の背景、その関係性については独自の解釈が加えられていて、物語ならではの演出も盛り込まれています。
史実を知っている方でも、その過程にどのようなドラマがあったのかを想像しながら読むことで、新たな視点を得られるでしょう。
- この作品をより深く理解するために参考になる本はありますか?
- いくつかあります。
本作は、哲学者・梅原猛氏の歴史観から着想を得た部分があり、とくに「隠された十字架 法隆寺論」などはその思想的背景を知る上で参考になります。
また、関裕二氏など、独自の視点から古代史を再解釈する作家の著作も、本作の「新説」に近い考え方を知る手がかりになるでしょう。
ただし、これらの書籍はあくまで補助的な資料です。まずは漫画そのものを純粋に楽しみ、そのあとで背景を深掘りしていくのがオススメです。
まとめ
「天智と天武―新説・日本書紀―」は、古代日本の歴史を舞台にしながら、史実の裏側にあるかもしれない“もうひとつの真実”を描いた、極めて意欲的な歴史漫画です。
これまでの歴史観にとらわれることなく、新たな解釈とドラマ性を融合させた本作は、読者の知的好奇心と感情の両面を揺さぶります。
本作の見どころを整理すると、以下の通りです。
- 大海人皇子が蘇我入鹿の子であるという設定や、中臣鎌足の正体を百済王子・豊璋とするなど、通説を覆す「新説」が物語の根幹をなしています。
- 天智と天武の兄弟関係を軸に、権力争い/復讐/執着といった濃密な感情が交錯し、ただの歴史ものに留まらない深いドラマが展開されます。
- 法隆寺の秘仏「救世観音」や聖徳太子の正体といった、歴史上の謎に切り込む要素も豊富で、推理小説を読むような知的な面白さが味わえます。
- 中村真理子による華やかで迫力ある画風が、登場人物の感情や場面の緊張感を視覚的に伝え、物語の魅力をより深めています。
- 兄弟でありながら、単なる愛や憎しみでは割り切れない関係性が描かれていて、一部の読者にはBL的な魅力としても受け取られています。
史実の枠に収まらない壮大な構想と、濃密な人間関係の描写が織りなす「天智と天武」は、歴史漫画という枠を超えた、上質なドラマ作品です。
歴史に興味がある方はもちろん、深い人間模様や重層的な物語を楽しみたい読者にとっても、強くオススメできる一冊です。
この作品を通じて、日本の古代に生きた人々の情念や、語られなかった「かもしれない物語」に思いを馳せてみてください。
きっと、記憶に残る特別な読書体験になることでしょう。
「天智と天武―新説・日本書紀―」をチェックする