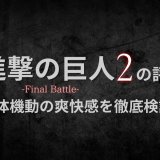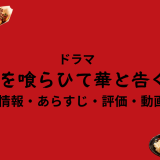2025年3月1日、経済アナリストとして長年活躍した森永卓郎さんの遺作となる著書「日本人「総奴隷化」計画1985-2029 アナタの財布を狙う「国家の野望」」が刊行されました。
この本には、森永さんが命を削ってまで伝えたかった“最後のメッセージ”が詰まっています。
日本の経済政策が、どのようにして国民一人ひとりの生活や自由を奪っていくのか?
鋭い視点と長年の知見をもとに、国家の裏側に潜む意図を明らかにしています。
森永さんは、2025年1月28日に67歳で亡くなられました。
生前、自らがステージ4のすい臓がん(原発不明がん)と公表し、病と闘いながらも、最後の最後まで執筆を続けました。
本書は、40年以上にわたる経済研究の集大成であると同時に、彼が読者に託した「遺書」のような存在でもあります。
国民の未来を案じる深い思いが、一文一文からにじみ出ています。
この記事では、本の情報や概要、他の読者の声や書評を詳しく解説します。
読んでみたいと感じている方に、この本の魅力をお伝えします。
本の情報

| 出版年月 | 2025年3月1日 |
| 著者/編集 | 森永卓郎 |
| 出版社名 | 徳間書店 |
| 発行形態 | 単行本(ソフトカバー) |
| ページ数 | 220P |
| 価格 | 1,600円(税別) |
| ISBNコード | 9784198659943 |
目次
- 高すぎたアメリカへのツケ
- 奴隷化計画を推進した小泉純一郎内閣
- 日本人を奈落の底に突き落とすザイム真理教
- 急所を握られた安倍政権の末路
- 奴隷化が加速する日本社会
- 新NISAは「地獄の入り口」
- 脱奴隷化のための「一人社会実験」
- 私の晩年
- 「グローバル資本主義」は崩壊する
本の概要

本書は全9章で構成されていて、それぞれの章で日本経済の本質に深く切り込んでいます。
第1章から第5章までは、日本の経済政策がどのように変化してきたのか?
その歴史と現在の状況を丁寧にひも解いています。
続く第6章では、新NISA制度に潜む落とし穴を明らかにし、第7章と第8章では、森永氏自身の体験を交えながら、私たちが直面する経済的な困難にどう立ち向かうべきかを示しています。
そして最終章では、グローバル資本主義の未来について、独自の視点から予測がなされています。
この本の核心にあるのは、「日本人総奴隷化計画」という衝撃的なテーマです。
著者は、1985年から2029年にかけて進行しているとされるこの“計画”の正体に迫り、その背後にある政治や経済の動きを鋭く追及しています。
私たちが年々重く感じている税負担や、削られていく社会保障、そして一向に上がらない賃金。
こうした生活の苦しさの原因を探りながら、森永氏は歴代の政権や官僚の責任を浮き彫りにします。
とくに注目したいのは、新NISA制度の危険性や、株価暴落によって始まる老後破綻のシナリオ。
さらに、財務省主導の増税方針がどのように庶民の生活を圧迫しているのかなど、生活に直結する問題が数多く取り上げられています。
森永氏はこうした状況を「奴隷化」と捉え、その流れを断ち切るための“脱奴隷”の具体策を本書で提示しています。
タイトルにある「1985-2029」という期間は、日本経済の転機であるバブル経済の幕開けから、著者が予測する大きな変化の到来までの44年間を意味しています。
森永氏はこの長い時間軸の中で、日本人の生活がどう変わってきたのかを克明に記録し、その裏で進行してきた「総奴隷化計画」の全貌を浮き彫りにしようとしています。
「日本人「総奴隷化」計画1985-2029」をネットで調べた他の読者の声

発売されたばかりということもあり、「日本人「総奴隷化」計画1985-2029」に関するレビューはまだ多くはありません。
しかし、これまでの森永卓郎氏の著作に寄せられた評価を見ると、本書への期待の高さが伝わってきます。
「森永氏の本を読むと、普段は見えにくい政策の裏側がよくわかる。とても勉強になる」
そんな声は、過去の著作でも多く寄せられていて、今回の遺作にも同様の評価が集まることが予想されます。
とくに、「具体的な事例が豊富で、初心者でも理解しやすい」「難しい経済の話も、かみ砕いて書かれている」といった意見が目立ちます。
森永氏の読み手に寄り添ったやさしい解説スタイルが、多くの読者に支持されている理由でしょう。
また、「資産形成や老後の備えについて、深く考えるきっかけになった」という感想も見受けられます。
本書もまた、単なる批判にとどまらず、将来を見据えた生き方を問いかける一冊になっているようです。
中には「読むことで危機感を抱いた」「知らされていない事実が多くて衝撃を受けた」といった声もあり、日本の経済状況に対する警鐘としての側面も感じさせます。
そして何より、「これは命をかけて書いた最期のメッセージだと思うと、読む側にも覚悟が必要だ」という真摯な意見もありました。
森永氏が託した警告と願いを、どう受け取るかは私たち一人ひとりに委ねられています。
「日本人「総奴隷化」計画1985-2029」の評価と書評

森永卓郎氏の遺作となった「日本人「総奴隷化」計画1985-2029」は、読み手に強烈な印象を与えるタイトルとともに、深い洞察に満ちた一冊です。
本書は、日本の経済政策が私たちの暮らしにどう影響を与えてきたのか、そしてこれからどこへ向かうのかを解き明かそうとしています。
注目すべきは、森永氏が40年以上にわたり積み重ねてきた経済アナリストとしての経験が、この一冊に凝縮されている点です。
バブル経済の崩壊から、現在の停滞期、そして未来に向けた展望まで、1985年から2029年にわたる流れを丁寧にたどっています。
これまでの実績をふまえた分析には重みがあり、読み応えも十分です。
中でも印象的なのは、「ザイム真理教」という言葉を用いた財務省批判です。
森永氏は、官僚主導で進められてきた経済政策のあり方に疑問を投げかけています。
この視点は、今まで意識しなかった構造的な問題に気づかせてくれるきっかけにもなるでしょう。
さらに、新しい制度として導入された新NISAに対しても、「地獄の入り口」と厳しく警鐘を鳴らしています。
また、「日経平均株価が2000円まで暴落する」という予測は、多くの人にとって驚きと不安を与える内容です。
こうした指摘は、私たちが資産や将来設計について見直すきっかけとなるかもしれません。
タイトルにある「総奴隷化計画」という表現にはやや強い印象があるかもしれませんが、それもまた、問題の深刻さに気づいてもらいたいという著者の意図の表れだと考えられます。
本書では、政府や財務省に対する辛口の批判も見受けられますが、それは長年の観察と実証を重ねてきた森永氏ならではの視点です。
とはいえ、すべてをうのみにせず、自分自身の視点を持ちながら読むことが大切です。
最終章で語られる「グローバル資本主義の崩壊」という大胆な予測も、本書の大きな見どころの一つです。
この未来像の是非は、今後の経済の動向と照らし合わせて見守っていく必要があるでしょう。
総じて、本書は日本経済の根本に切り込みつつ、私たちの生き方にも問いを投げかける、示唆に富んだ一冊です。
森永氏の経済アナリストとしての集大成を読み解くことで、見えてくる「真実」もあるかもしれません。
「日本人「総奴隷化」計画1985-2029」のオススメの読者層

森永卓郎氏の遺作である本書「日本人「総奴隷化」計画1985-2029」は、読み応えのある内容と深い問題提起が詰まった一冊です。
とくに以下のような方には、強くオススメしたい内容となっています。日本の経済政策に関心がある方
- 日本の経済政策に関心がある方
1985年から現在、そして未来へと続く日本経済の流れを、政策の変遷とともに丁寧にたどっています。
表向きの報道だけでは見えてこない“裏側”を知る手がかりとなるでしょう。 - 将来の生活設計や資産の管理を考えている方
新たな制度として話題の「新しい少額投資制度(新NISA)」に潜む問題点や、株式市場の急落に対する警告などが具体的に示されています。
今後の暮らしに不安を感じている方には、多くの気づきがあるはずです。 - 日本社会の仕組みに疑問を抱いている方
「総奴隷化」という表現に象徴されるように、経済を超えて社会全体の構造にまで踏み込んだ考察が展開されています。
働き方、生活格差、制度疲労など、現代社会に潜む問題を多角的に読み解ける一冊です。 - 経済の見方や分析の方法を学びたい方
森永氏が長年にわたって培ってきた経済の分析手法が、随所に盛り込まれています。
理論だけでなく、現実の動きと照らし合わせながら学べる実践的な内容です。 - 自分の頭で考える力を鍛えたい方
政府の方針や報道をそのまま受け取るのではなく、自分で考え、判断する力が求められる時代です。
本書の挑戦的な主張は、そうした思考力を養う上で格好の材料になるでしょう。
もし一つでも心に引っかかる項目があれば、ぜひ一度ページをめくってみてください。
森永氏が命をかけて書き残した言葉の数々が、あなたの考え方に新たな視点を与えてくれるかもしれません。
「日本人「総奴隷化」計画1985-2029」の類似作品の紹介

「日本人「総奴隷化」計画1985-2029」を読んで、もっと深く日本経済の真実に迫りたい。
そんな方にオススメしたい関連書籍をご紹介します。
いずれも森永卓郎氏の手による著作で、本書とつながる重要な視点が盛り込まれています。
- 「ザイム真理教――それは信者8000万人の巨大カルト」(2022年)
「ザイム真理教」という独自の言葉で、財務省中心の経済運営を鋭く批判した話題作です。
官僚主導の増税や緊縮財政が、どのように国民生活に影を落としているのかを掘り下げています。
本書の前段として読むことで、森永氏の問題提起の背景がより鮮明になるでしょう。 - 「書いてはいけない――日本経済墜落の真相」(2022年)
日本経済の“失敗の連鎖”を、具体的な政策と数値をもとに明らかにした一冊です。
本書と同様に、報道では語られない経済の裏側に切り込み、読者に考える材料を与えてくれます。
「総奴隷化計画」と並行して読むことで、相互に補完し合う視点が得られます。 - 「長生き地獄 資産尽き、狂ったマネープランへの処方箋」(2022年)
老後資金の枯渇や生活不安が広がる中、長生きが「喜び」ではなく「負担」になりつつある現実に警鐘を鳴らしています。
「総奴隷化計画」で語られていた老後リスクについて、さらに詳しく知りたい方にはとくにオススメです。
これらの書籍を通して、森永氏が訴えてきた日本経済の“真の問題”をより深く理解することができます。
気になるテーマがあれば、ぜひ手に取ってみてください。
読めば読むほど、私たちが見過ごしてきた現実が見えてくるはずです。
著者について

本書「日本人「総奴隷化」計画1985-2029」の著者である森永卓郎(もりなが・たくろう)氏は、経済の本質をわかりやすく伝えることで多くの人々に親しまれてきた経済評論家です。
1957年、東京都目黒区に生まれた森永氏は、東京大学経済学部を卒業後、昭和55年に日本専売公社(現・日本たばこ産業株式会社)へ入社しました。
その後、経済企画庁への出向を経て、三井情報開発株式会社や三和総合研究所(後の三菱UFJリサーチ&コンサルティング)などで経済調査の実務を積み重ねていきます。
平成18年からは、獨協大学経済学部の教授として教育にも力を注ぎました。
専門はマクロ経済、労働問題、経済政策と幅広く、アニメや漫画などを通じて現代文化を経済的に分析する“オタク文化論”でも知られています。
また、テレビやラジオにも数多く出演し、庶民の目線を大切にした親しみやすい解説で、多くの視聴者に支持されてきました。
2003年には「年収300万円時代を生き抜く経済学」が大ヒットし、世間に強いインパクトを与えました。
令和5年11月、末期がんの告知を受けた後も筆を止めることなく、最後まで執筆活動を続けた森永氏。
本書は、そんな彼の“遺書”ともいえる最後のメッセージとして世に送り出された一冊です。
2025年1月28日、67歳でこの世を去りましたが、その言葉と想いは多くの読者の中に生き続けています。
「日本人「総奴隷化」計画1985-2029」のよくある質問

- タイトルにある「1985-2029」は何を意味しているのですか?
- 1985年は「プラザ合意」が交わされた年です。
この出来事を、森永氏は「日本人総奴隷化の始まり」と位置づけています。
一方、2029年は著者が予測する“経済の転換点”とされていて、日本社会の流れが大きく変わる年になると見られています。
- 「奴隷化」とは具体的にどういう状態を指しているのですか?
- 税金や社会保険料の負担が増え続ける一方で、賃金は伸び悩み、生活はますます苦しくなっています。
その結果、経済的に自由を奪われ、特権階級に管理・支配されるような社会構造が生まれている。
森永氏は、こうした現状を「奴隷化」と表現しています。
- 新しい少額投資制度(新NISA)についてはどう評価されていますか?
- 森永氏は新NISA制度を「地獄の入り口」と厳しく非難しています。
その理由は、制度自体がバブル的であり、将来的に株式市場が大暴落する可能性があるからです。
とくに、老後の資産形成をこの制度に頼ることには大きな危険があると指摘しています。
- 「脱奴隷化」の方法とは何でしょうか?
- 著者自身が実際に行った「一人社会実験」から得た知見に基づき、「幸福の絶対法則」という独自の考え方が示されています。
そこでは、閉塞感を取り払い、不安を減らしながら、自分らしく生きるための実践的なヒントが具体的に紹介されています。
まとめ
「日本人「総奴隷化」計画1985-2029」は、経済アナリスト・森永卓郎氏が命を懸けて世に残した最後の著作です。
本書には、日本という国の経済がどのように変化し、どのように国民の生活に影響を与えてきたのか、その核心が凝縮されています。
とくに注目すべき内容は、以下のといてです。
- 昭和60年の「プラザ合意」以降に始まった構造的な経済の歪みに切り込み、日本社会の変遷を分析
- 財務省をはじめとする官僚主導の経済政策に対し、「ザイム真理教」という独自の言葉で痛烈に批判
- 新たな少額投資制度(新NISA)の落とし穴と、株式市場の暴落リスクについて警鐘を鳴らす
- 閉塞感を打ち破るための「脱奴隷化」の具体的な方法を提示し、将来への備えを呼びかける
森永氏は、難解な経済の話をあくまでも庶民の視点で語り、読む人一人ひとりに考えるきっかけを与えてくれます。
本書は、経済に関心のある方だけでなく、これからの暮らしに不安を感じているすべての方にとって、大切な「気づき」を与えてくれる一冊です。
未来を他人任せにせず、自分の手で選び取りたいと願う人にこそ、手に取ってほしい一冊です。